2025/05/31
ブログ更新:健康寿命を守る5月の“気づき”とは?初夏に始める介護予防の新習慣【山梨/デイサービス】
はじめに
5月は、「気候が穏やかで動きやすい季節」と言われますが、実は高齢者にとって身体と心に変化が起きやすい“節目の月”です。
・気温の変化で体がだるくなりやすい
・ゴールデンウィーク明けで生活リズムが乱れがち
・外出の機会が減って活動量が落ちやすい
これらはすべて、フレイル(虚弱)や認知症、筋力低下といった“健康寿命を縮めるリスク”の始まりでもあります。
今回は、5月に配信した介護予防に関する8本+追加2本の記事を振り返りながら、「なぜ5月が介護予防の重要なタイミングなのか」「どんな気づきが大切なのか」をまとめ、6月の備えにつなげていきます。
1. 5月は“ゆるやかに衰える”リスクが高い月
5月は季節の変わり目であり、以下のような“生活リズムのゆるみ”が起こりやすい時期です:
「リスク→内容」
・活動量の低下→気温差や疲れで外出を控えがちになる
・筋力低下の始まり→「立ち上がりづらい」「歩くのが遅くなった」などの小さな変化
・水分不足、脱水→気づかないうちに始まる“隠れ熱中症”
・気分の沈み、無気力→ゴールデンウィーク後の気持ちの変化
・社会的孤立→行事が終わり、会話や外出の機会が減少
このような“小さな変化”に気づかずに過ごしていると、知らないうちにフレイル・認知症・要介護状態に近づいていくのです。
2. 「未病」に気づく力が、健康寿命を左右する
5月に重点的に取り上げたのが、「未病(みびょう)」という考え方です。
健康診断では問題がないのに、
・なんとなく疲れやすい
・食欲が落ちてきた
・外に出るのが面倒になった
こうした“未病サイン”は、予防医療や介護予防の現場で重視されている初期兆候です。
5月は、「自分の変化」に気づきやすい季節でもあります。
日々のちょっとした違和感に耳を傾けることで、未来の病気や介護状態を回避できるかもしれません。
3. 5月の介護予防10テーマから見る、注目の「気づき」
「テーマ→着目ポイント」
・気温差による筋力低下→外出が減り、下半身が衰えるサインに気づけたか?
・水分不足による脱水→熱中症の一歩手前を予防できたか?
・歩く力の衰え→「歩きづらい」と思ったら要注意
・認知症予防の生活習慣→会話・運動を意識できたか?
・転倒予防と室内運動→雨の日でも体を動かす仕組みはできたか?
・地域交流のすすめ→人とのつながりを持てたか?
・フレイル初期サイン→食欲、体重、意欲の変化に気づけたか?
・立ち上がり筋力の低下→「よいしょ」が増えていないか?
・健診では見えない未病→自覚症状の変化に敏感になれたか?
➡ これらの視点は、今後の生活改善と予防行動のヒントになります。
4. 6月に向けて意識したいこと
6月は梅雨入りの季節。 以下のような新たなリスクが浮上します。
☔ 室内生活が長くなる → 活動量のさらなる低下
→ 椅子に座ったままでできる体操・スクワットを日課に
☁ 気圧変化による不調 → 自律神経・気分の不安定化
→ 睡眠・入浴・朝の光を意識して生活リズムを整える
🧂 暑さ・湿気 → 熱中症・栄養不足が加速
→ 水分補給だけでなく、たんぱく質・ミネラルも意識
➡ 5月に気づいた「弱点」や「違和感」を放置せず、6月に改善アクションを移すことがとても大切です。
まとめ:5月は“気づき”の月。6月は“行動”の月に。
5月に見えてきた、自分自身や家族の「小さな変化」。
それを見逃さずに受け止め、6月は「改善・実践」に移していくタイミングです。
✅ 未病のサインをキャッチできたか?
✅ 食事・運動・交流を日常に取り入れられたか?
✅ 雨の日でも継続できる“仕組み”はできているか?
健康寿命を延ばす一番の方法は、“早く気づいて、小さく始める”ことです。
6月も、身体と心を見つめながら、ゆるやかに、でも確実に、介護予防を続けていきましょう。

![ブログ更新:健康寿命を守る5月の“気づき”とは?初夏に始める介護予防の新習慣【山梨/デイサービス】]()
2025/05/25
ブログ更新:健康診断の結果だけで安心していませんか?“未病”と介護予防のすすめ【山梨/デイサービス】
はじめに
「健康診断は異常なしだったから、安心だ」
――そんな風に思っていませんか?
実は、健康診断では見えない“体のサイン”こそが、将来のフレイルや介護リスクを知らせているかもしれません。
「未病(みびょう)」とは、病気と診断される前の“健康ではない状態”。
放置すれば高血圧、糖尿病、フレイル、認知症といった深刻な疾患に進行する可能性があります。
この記事では、健康診断だけに頼らず「未病」に気づき、予防する方法をわかりやすく解説します。
1. 「未病」とは?今注目される“予防の考え方”
✅ 「未病」=病気ではないけど健康でもない状態
未病は、体に小さな異変が起き始めている段階。まだ検査では異常が出なくても、生活習慣や自覚症状に“違和感”が出始める状態を指します。
✅ 厚生労働省や自治体も注目
現在、多くの自治体が「未病対策」に力を入れています。なぜなら、未病の段階で気づき・対処できれば、将来の介護・医療費を抑えられるからです。
2. 健康診断でわからない“未病のサイン”
以下のような「ちょっとした不調」、心当たりはありませんか?
「体の変化→こんなサインに注意!」
・疲れやすい→少しの動作で息切れする、疲労感が抜けない
・食欲がない→以前より量が食べられない、体重が減ってきた
・睡眠の質が悪い→夜中に何度も起きる、熟睡感がない
・活動量が減った→外出回数が減った、家で過ごす時間が増えた
・気分が沈みがち→意欲がわかない、笑うことが減った
➡ これらの変化は「加齢」ではなく「未病」のサインかもしれません。
3. “未病”のうちに対処するメリット
✅ フレイル・要介護状態を未然に防げる
フレイル(加齢に伴う虚弱状態)は、未病と密接に関係します。
「最近疲れやすい」「ちょっとやせた」といった未病サインを放置すると、筋力低下→転倒→入院→寝たきりという悪循環に陥ることも。
✅ 生活習慣を見直すことで改善できる
未病の段階であれば、薬や手術ではなく「生活の見直し」だけで十分に改善可能。
自分でできる「セルフケア力」が、今後の健康を左右します。
4. “未病”を防ぐ3つのセルフケア習慣
【1】動く:毎日少しでも体を動かす
・買い物はあえて遠回りする
・テレビのCM中に足踏み体操
・朝夕のウォーキング(10分〜でもOK)
➡ 「運動不足」は未病の代表格。“動かすことで気づける”ことも多いです。
【2】食べる:たんぱく質+水分の意識
・朝食に卵、納豆、ヨーグルト
・昼は肉、魚で主菜を確保
・味噌汁やスープで水分、塩分を補給
➡ 体力のもとになる「たんぱく質」が足りていないと、筋肉も免疫力も落ちます。
【3】つながる:社会との関わりを持つ
・地域の体操教室
・健康サロン
・家族との定期的な電話、会話
・ボランティアや趣味の場に顔を出す
➡ 「人とつながること」自体が、最高の未病対策になります。
5. 健康診断+“自分の感覚”が最強の予防
✅ 健診は「スタート」であって「ゴール」ではない
健診の数値に異常がないからといって、「健康である」とは限りません。
日々の暮らしのなかで、「前と違うな」と感じたら、それが最も大切なサインです。
✅ 自分の体を一番知っているのは“自分自身”
・眠りが浅い
・気分が晴れない
・階段がきつくなった
➡ こうした小さな気づきをスルーしないことが、健康寿命を守る第一歩です。
まとめ:「未病」に気づける人は、未来も健康でいられる
✅ 健康診断で異常なしでも、「未病」は進行していることがある
✅ 疲れ・体重減少・活動量減少などのサインに注目
✅ “動く・食べる・つながる”の3つの生活習慣で予防できる
✅ 自分の感覚に耳を傾け、早めに行動することが何よりの介護予防
健康とは「病気がないこと」ではなく、毎日を元気に暮らせること。
未来の自分のために、“未病のサイン”に気づける習慣を、今日から始めてみませんか?
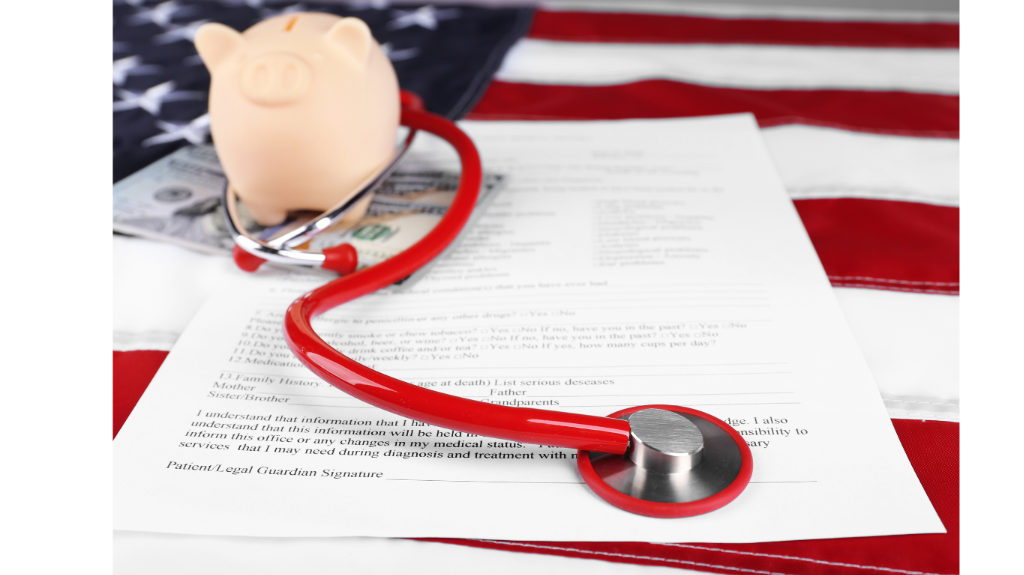
![ブログ更新:健康診断の結果だけで安心していませんか?“未病”と介護予防のすすめ【山梨/デイサービス】]()
2025/05/24
ブログ更新:立ち上がりにくさ”は老化のサイン?下半身筋力チェックと改善法【山梨/デイサービス】
はじめに
「椅子から立ち上がるのが前よりつらくなった気がする…」
「よいしょ、が口癖になってきたかも」
――そんな“ちょっとした変化”、見逃していませんか?
実は、椅子からの立ち上がり動作は、日常生活動作(ADL)のなかでも下半身の筋力・バランス・柔軟性が総動員される動作。
つまり、「立ちにくい=老化のサイン」「フレイルの入り口」である可能性があるのです。
この記事では、立ち上がり動作が示す身体の状態と、簡単なセルフチェック・改善トレーニング法を、理学療法士の視点でわかりやすく解説します。
1. なぜ「立ち上がり」が重要なのか?
✅ 日常生活に直結する動作
椅子・トイレ・布団など、“座っている状態から立つ”という動作は1日に何度も行われる基本動作。
ここに支障が出ると、自立した生活が一気に難しくなります。
✅ 下半身の衰え=フレイルの始まり 特に使われる筋肉は:
・大腿四頭筋(ももの前)
・臀筋(お尻)
・腸腰筋(股関節まわり)
➡ これらの筋肉は「歩行・階段昇降・バランス保持」に直結しており、転倒や寝たきりリスクにもつながります。
2. チェックしてみよう!立ち上がり筋力の簡易テスト
以下は、全国の介護予防教室などでも使用されている簡単な筋力チェック法です。
✅ 【立ち上がりテスト】
方法:
① 高さ40cm程度の椅子を用意
② 腕を組んで(または体の前でクロス)、手を使わずに立ち上がる
③ 一度ではなく、5回連続で立ち上がれるか試してみる
判定:
スムーズに立てない・途中でよろける → 要注意!
時間がかかる・疲れてしまう → 下半身筋力低下の可能性
3. 今日からできる!下半身筋力の改善トレーニング
特別な器具や場所は不要。自宅で、椅子1つでできる運動をご紹介します。
✅ 【1】椅子スクワット
やり方:
① 椅子に浅く腰掛ける
② 手を前に出し、ゆっくり立ち上がる
③ 立ち上がったら数秒キープし、またゆっくり座る ➡ 5〜10回 × 1〜2セット(疲れすぎない程度)
ポイント:
膝が前に出すぎないよう注意
背筋を伸ばして、お尻と太ももで立ち上がる意識
✅ 【2】もも上げ運動(座位)
やり方:
① 椅子に座り、背筋を伸ばす
② 片足ずつ太ももをゆっくり上げて3秒キープ
③ 左右交互に10回ずつ
➡ 腸腰筋(ももの付け根)の強化に有効
✅ 【3】足踏み運動(立位)
やり方:
① 壁や椅子に手を添えて立つ
② その場で足踏み(30〜50回)
③ 可能であれば、目を閉じずに姿勢を保つ意識
➡ バランス感覚と下半身の持久力を高める
4. 継続のコツ:生活に“溶け込ませる”
✅ 「ながら運動」で習慣化 ・歯磨き中にかかと上げ
・テレビを見ながら足踏み
・お湯を沸かす間に椅子スクワット1回
➡ 「特別な時間を取らない」ことが継続のカギです。
✅ 家族と一緒に取り組む
「立ち上がり対決しよう!」
「何回できるかチャレンジ!」
➡ ゲーム感覚にすることで楽しく継続できます。
5. 立ち上がりにくさは“介護予防”の分かれ道
「立つ・歩く・座る」といった基本動作がスムーズにできるかどうかは、将来的な介護リスクを大きく左右する要素です。
「最近立ち上がるのが遅くなった」
「立ち上がるときに“どっこいしょ”と言うようになった」
「低い椅子から立つのを避けるようになった」
➡ これらの変化があれば、すぐに改善行動をスタートしましょう。
まとめ:立ち上がる力を、今こそ見直そう!
✅ 椅子からの立ち上がりは、下半身の筋力・柔軟性・バランスのバロメーター
✅ 簡単なチェックとトレーニングで、筋力低下を防げる
✅ 継続の工夫と家族のサポートで、習慣化しやすくなる
「立つこと」がつらくなると、生活の自由度も一気に下がってしまいます。
だからこそ、“立ち上がりやすさ”を守ることは、自分らしい生活を守ること。
今日から1歩、始めてみませんか?

![ブログ更新:立ち上がりにくさ”は老化のサイン?下半身筋力チェックと改善法【山梨/デイサービス】]()
2025/05/18
ブログ更新:こんな症状があれば要注意!フレイル初期サインと対処法【山梨/デイサービス】
はじめに
「年だから仕方ない」
――そんな言葉で見逃していませんか?
実は、“ちょっとした体や心の変化”が、フレイル(虚弱)のサインである可能性があります。
フレイルとは、「健康と要介護の中間」にあたる状態。見過ごして放置すると、筋力や体力の低下が加速し、転倒・寝たきり・認知症などのリスクが高まります。
この記事では、フレイルの初期サインと、自宅で今すぐ始められる対策を、理学療法士の視点でわかりやすく解説します。
1. フレイルとは?なぜ見逃されやすいのか
✅ フレイル=心身の“予備力”が落ちてきた状態
加齢により、筋力・認知機能・免疫力などの「生活を維持する力」が少しずつ低下していくことを指します。
✅ 病気ではないからこそ気づきにくい
・検査数値には現れない
・本人も「年のせい」と思いがち
・家族も「少し元気がないだけかな」と見過ごしやすい
➡ しかしこの段階で気づいて対処できれば、健康な状態に戻すことも可能です。
2. 要注意!フレイルの初期サインとは?
以下のような変化に思い当たりませんか?
「項目→初期サインの例」
・筋力→握力が弱くなった、ペットボトルの蓋が開けにくい
・体重→最近やせた、食欲が落ちた
・活動→外出の回数が減った、家でじっとしている時間が増えた
・疲労→何をするのもおっくう、疲れやすい
・認知→会話が減った、名前が出てこないことが増えた
・心の状態→意欲が低下している、気持ちが沈みがち
特に、「半年で2〜3kg以上体重が減った」「週に1回も外出していない」といった変化がある場合、早めの対応が必要です。
3. チェックしてみよう!「簡易フレイルチェック」
以下の5項目に「はい/いいえ」で答えてみましょう。
・最近6ヶ月で、体重が2kg以上減った
・筋力が低下した(ペットボトルが開けづらい)
・歩く速度が遅くなったと感じる
・身体の活動量が減った(外出や家事が億劫)
・「疲れやすい」とよく感じる
✅ 3つ以上「はい」があれば“フレイルの疑いあり”
1〜2つでも、注意して生活を見直すことが大切です。
4. 今日から始められる!フレイル予防3つの柱
✅ 【1】運動:筋力維持が最優先
フレイル予防の中心は、下半身の筋肉を維持・強化することです。
おすすめ運動:
・椅子スクワット(5回×2セット)
・もも上げ運動(片足ずつ10回)
・足首回し+かかと上げ(10回ずつ)
ポイントは、毎日“少しずつでも続けること”。時間ではなく“習慣化”がカギです。
✅ 【2】栄養:たんぱく質と水分をしっかり
筋肉は「動かす」だけでなく、「栄養を与える」ことも必要です。
特に、たんぱく質・ビタミンD・水分の摂取を意識しましょう。
「食材→効果」
_卵・納豆・豆腐→良質なたんぱく質
_魚・鶏肉→筋肉の合成を助けるアミノ酸
_牛乳・ヨーグルト→骨や筋肉を守るビタミンD
_味噌汁・スープ→水分補給も同時にできる
✅ 【3】社会参加:心も一緒に動かす
・近所の体操教室やデイサービス
・家族や友人との会話、電話
・地域のイベントやボランティア活動
➡「人とつながる」「誰かと動く」ことは、フレイルを遠ざける最高の薬です。
5. 家族・周囲ができるサポートとは?
✅ 見守るより“気づく”
・食事の量が減っていないか?
・会話のテンポが遅くなっていないか?
・表情が乏しくなっていないか?
➡ 日々の観察が、早期の気づきに繋がります。
✅ 声かけ・同行で“行動”を促す
「一緒に散歩に行こう」
「今日のお昼、タンパク質たっぷりの献立にしたよ」
「◯◯さんも来るから、ちょっと見に行ってみない?」
➡ 指示ではなく共感と同行が習慣化のポイントです。
まとめ:気づくことが、最大の予防になる
「ちょっと元気がないな」「最近静かだな」
――その“なんとなく”が、フレイルの始まりかもしれません。
✅ 初期サインを見逃さないこと
✅ 運動・栄養・社会参加を小さく始めること
✅ 家族や地域で「気づき合うこと」
それだけで、健康でいられる時間は確実に延びていきます。
ぜひ今日から、フレイル予防を意識してみてください。

![ブログ更新:こんな症状があれば要注意!フレイル初期サインと対処法【山梨/デイサービス】]()
2025/05/17
ブログ更新:介護予防×地域交流イベントのススメ〜5月の外出機会を増やそう〜【山梨/デイサービス】
はじめに
「介護予防=運動や食事のこと」と思っていませんか?
実は、人とのつながり(=社会参加)こそが、認知症予防・フレイル予防に大きな効果を持つことが、近年の研究でも明らかになっています。
特に高齢者にとって、「出かける」「話す」「誰かと一緒に過ごす」という行動は、心と体を若々しく保つうえで非常に重要です。
この記事では、5月という“絶好の交流シーズン”に焦点を当て、地域イベントやサロン活動などへの参加が、どのように健康寿命を延ばすのか、また、外出が苦手な方でも始めやすい工夫をご紹介します。
1. 社会参加が「介護予防」につながる理由
✅ 孤立は最大のリスク因子のひとつ
高齢者の閉じこもりは、筋力や認知機能の低下、うつ状態を引き起こしやすく、要介護状態に直結するリスクがあります。
「孤立状態の影響→内容」
_運動量の低下→外出しない=歩かない=筋力低下
_刺激の欠如→会話や発見がなく、脳が休眠状態に
_気力の低下→無気力・不安・不眠などが続く
✅ 社会参加で得られる効果は“全方位的”
_歩いて会場へ行く=運動機会の確保
_会話する=認知機能の活性化
_笑う・食べる=ストレス軽減・QOL向上
➡ つまり、地域とのつながりは「介護予防の総合栄養剤」とも言えるのです。
2. 5月は外出・交流に最適な季節!
✅ 気候が穏やかで、移動もしやすい
寒すぎず、暑すぎず、湿気も少ない5月は、「何かを始める」「外に出る」には最適なタイミングです。
✅ 行事や地域イベントも豊富
・健康フェア、バザー、文化祭などの地域催し
・ボランティア体験、ふれあいサロンなど ・行政主催のプログラム
・季節の花を楽しむウォーキングイベント など
➡「きっかけがない…」という方でも参加しやすい時期です。
3. 交流が苦手でも始めやすい“ゆるいつながり”
✅ 運動系サロンや健康教室から始めよう
・初対面でも会話を強要されにくく、「ただ一緒に体を動かす」だけでも十分な効果があります
・理学療法士や保健師がいる場なら安心感も◎
✅ 見学・付き添いから始めるのもOK
「まずは様子を見に来ただけ」でも歓迎される地域イベントが多く、参加のハードルが低いのが特徴です
4. 家族ができる“そっと背中を押す工夫”
✅ 声かけの工夫
NG:「出かけたほうがいいよ」
OK:「一緒に近くまで行ってみようか?」「今日は◯◯さんも来るみたいだよ」
➡目的を“交流”に置くより、「見に行く」「体験してみる」といった行動ベースの声かけが効果的です。
✅ 送迎・付き添いで不安軽減
「帰りは私が迎えに行くよ」など、最初の1歩を後押しする支援が非常に大きな力になります。
5. 介護予防としての“地域の力”
✅ 地域包括支援センターや通いの場を活用
多くの市町村では、高齢者向けの通いの場(通所型介護予防事業)を設けており、
・体操教室 ・栄養講座
・おしゃべりカフェ
など、 多様なニーズに応じたプログラムが実施されています。
まとめ:「動く・話す・笑う」が、明日の元気をつくる
5月という“始めやすい季節”をきっかけに、「介護予防」の新しい一歩を踏み出しませんか?
✅ 社会参加は、筋力・認知機能・心の健康すべてに効果的
✅ 地域イベントやサロン活動は、楽しく自然につながれる機会
✅ 家族や地域のちょっとした支援が、安心の背中押しになる
まずは「少し外に出てみる」ことから。
その一歩が、健康寿命を延ばし、人生の質を高める第一歩になります。

![ブログ更新:介護予防×地域交流イベントのススメ〜5月の外出機会を増やそう〜【山梨/デイサービス】]()
2025/05/11
ブログ更新:5月は“水分補給”の始めどき!高齢者の熱中症対策ガイド【山梨/デイサービス】
はじめに
「熱中症って真夏の話じゃないの?」
そう思って油断していませんか?
実は、熱中症は5月からすでにリスクが高まっています。
特に高齢者は、自分で暑さやのどの渇きに気づきにくく、軽い脱水から一気に重症化することも。
この記事では、「なぜ5月から熱中症に気をつけるべきなのか」から、「高齢者に適した水分補給のコツ」まで、介護予防・健康寿命延伸の観点からわかりやすくご紹介します。
1. 5月から熱中症リスクが高まる理由
✅ 身体がまだ暑さに慣れていない
5月は気温が急上昇する日がある一方で、体はまだ“春仕様”。
汗をかく機能や体温調整が追いつかず、体に熱がこもりやすい状態です。
✅ 室内の暑さに気づきにくい
風通しの悪い室内は熱がこもりやすく、特に高齢者はエアコン使用を控えがち。**“隠れ熱中症”**が起こりやすくなります。
✅ 自覚症状が少ない
高齢者は「喉の渇き」を感じにくく、脱水が進行していても気づきにくい傾向にあります。
2. 熱中症の初期サインに気づこう
症状が進んでからでは遅い!
次のようなサインが出たら、水分・塩分補給を意識しましょう。
「症状注意→ポイント」
_なんとなく元気がない→会話が減る、ぼーっとしている
_尿の色が濃い・量が少ない→脱水のサイン、トイレ回数もチェック
_軽い頭痛・めまい→初期の熱中症に多い
_症状食欲がない・だるい→胃腸の水分不足・体温上昇の影響
➡ 「ちょっと変だな」と思ったら、“水分補給+休憩”が最優先です。
3. 高齢者に適した水分補給のコツ
✅ ポイント①「喉が渇く前に飲む」
「喉が渇いてから」では遅い場合が多いので、時間を決めて定期的に飲みましょう。
「タイミング→目安量(コップ1杯=約200ml)」
_起床時→1杯(白湯や常温の水)
_午前中→1〜2杯(お茶など)
_昼食時→1杯+汁物など
_午後→1〜2杯(間食や運動前後)
_夕食時→1杯+味噌汁など
_就寝前→1杯(寝る30〜60分前が理想)
✅ ポイント②「食事からも水分をとる」
水だけでなく、食事からの水分摂取も意識しましょう。
おすすめは:
_果物(みかん、スイカ)
_野菜(きゅうり、トマト)
_スープ、味噌汁、ゼリー、プリン
4. 塩分とミネラルもセットで補給
汗をかくと、水分だけでなく塩分やミネラルも失われます。
次のような食品を少量ずつ取り入れるのがおすすめです。
「食材→補給できる栄養」
_梅干し→塩分・クエン酸
_昆布・味噌→ナトリウム・カリウム
_スポーツドリンク(薄めて)→電解質・糖分
➡ 持病がある方は医師や栄養士に相談を。
5. 室内の“熱中症ゾーン”に注意!
高齢者は室内での熱中症が多いことをご存知ですか?
「場所→危険要素」
_台所→火を使って暑くなる、狭くて風が通らない
_トイレ→長時間こもりがち、換気が不十分
_洗面所→湿度が高いのに冷房がない
_和室→畳の熱こもり、通気性が悪い場合も
➡ 対策:扇風機・エアコンを早めにON! 室温は25〜28℃が目安です。
6. 家族や地域の支援も大切
✅ 声かけで意識づけ
「水分とった?」
「部屋暑くない?」
ちょっとした一言が大切です。
✅ 地域の見守りを活用
地域包括支援センターや介護予防教室では、季節に合わせた健康講座やチェックリストの提供があることも。活用して“予防のきっかけ”を増やしましょう。
まとめ:5月から始める熱中症対策で、健康寿命を守る!
熱中症は、夏の出来事ではなく“予防すべき生活習慣の問題”です。
特に高齢者は、症状が出る前の対策が命を守るカギになります。
✅ 喉が渇く前に、定期的に水分をとる
✅ 食事や間食でも水分+塩分を補う
✅ 室温管理と家族の声かけで早期予防を!
「まだ5月だから」と思わずに、今こそ始めることが大切です。

![ブログ更新:5月は“水分補給”の始めどき!高齢者の熱中症対策ガイド【山梨/デイサービス】]()
2025/05/10
ブログ更新:転倒リスク急上昇!雨の日の“安全な歩き方”と室内運動【山梨/デイサービス】
はじめに
「雨の日は滑りやすいから怖い」
「最近、家の中でもふらつくことがある」
そんな不安を感じたことはありませんか? 特に5月〜6月の梅雨シーズンは、転倒リスクが最も高まる時期です。外は濡れた路面、家の中も湿気で滑りやすくなり、足元が不安定に。しかも、活動量が減ることで筋力も落ちやすくなる“ダブルリスク”の時期でもあります。
この記事では、高齢者に多い転倒の原因と、雨の日に気をつけたい歩き方のコツ、そして室内でもできる簡単な運動をご紹介します。転倒によるケガを防ぎ、健康寿命を守るために、ぜひチェックしてみてください。
1. 雨の日はなぜ転倒しやすい?
✅ 滑りやすい靴・床面
・濡れた靴底、タイルや玄関マットなど、滑りやすい素材が危険
・特に玄関やスーパーの床は要注意!
✅ 視界が悪くなる
・傘をさして足元が見えない
・薄暗い夕方、黒い服
・路面の段差が見えにくい
✅ 身体のバランスが崩れやすくなる
・寒暖差で筋肉がこわばりやすく、ふらつきやすい状態に
・外出機会が減り、筋力が低下していることも要因
2. 転倒によるリスクは“想像以上”
転倒は単なる「ケガ」では終わりません。骨折→入院→寝たきりという連鎖が、高齢者ではよく見られます。
転倒による主な影響→内容
_大腿骨骨折→手術・入院、リハビリが必要になるケースも多い
_自信喪失→「もう外に出たくない」、引きこもり傾向に
_認知機能の低下→活動が減り、刺激が減ることで進行しやすい
➡ 転倒は身体面・精神面・社会性のすべてに影響を与える重大な出来事です。
3. 雨の日でも安心!歩き方のポイント5つ
✅ ① 靴の裏をチェック!
・濡れた路面に強い
・「すべり止め付き」の靴底を選びましょう
・雨用スニーカーや滑り止めカバーもおすすめ
✅ ② 歩幅はいつもより小さく
・足を大きく出すとバランスを崩しやすくなります
・小刻みで安定感のある歩き方を意識しましょう
✅ ③ 視線はやや前方に
・つま先を意識しすぎるとバランスを崩します
・2〜3歩先を自然に見るのが◎
✅ ④ 両手はなるべく空ける
・傘は軽量タイプを使い、荷物はリュックなどにまとめて
・転倒時に手が使える状態を確保
✅ ⑤ 玄関・スーパーの入り口は特に注意!
・水たまり、マット、タイル床などはスリップ注意ゾーン
・「滑るかも」と思ったら、そろそろ歩きで乗り切りましょう
4. 雨の日でもできる「室内運動」で転倒予防
活動量が減ると、筋力はあっという間に落ちていきます。 以下は、室内で簡単にできる転倒予防に効果的な運動です。
✅【1】椅子スクワット(下半身強化)
背もたれのある椅子を使って、立ち上がり→座るを繰り返す 5〜10回 × 2セット
➡ 太もも・お尻・体幹の筋力アップに
✅【2】かかと上げ(ふくらはぎ強化)
壁や椅子につかまりながら、かかとをゆっくり上げ下げ
10回 × 2セット
➡ 足首の可動域とバランス力を向上
✅【3】片足立ち(バランス力強化)
壁に手を添えながら、片足を浮かせて10秒キープ
左右各3回ずつから
➡ 転倒予防に直結するバランス機能を鍛えられます
5. 継続のコツと家族のサポート
✅ 毎日の生活動作とセットに
歯磨き中にかかと上げ テレビを見ながら足踏み運動 お茶を淹れる間に片足立ち 「ながら運動」を生活に組み込むのがコツです。
✅ 家族の声かけも効果大
「今日は運動した?」
「雨だけどスクワットだけでも!」など
雨の日こそ「動くきっかけ」を一緒に作ることが大切です
まとめ:雨の日こそ「転倒予防」に意識を!
雨の日の外出はリスクが高く、室内でも油断はできません。 だからこそ、今から“歩き方”と“筋力”を見直すことが、転倒を防ぎ、元気な毎日を守る第一歩です。
✅ 小さな歩幅、視線、靴のチェックで安全な歩行を
✅ 雨の日でもできる室内運動を継続
✅ 家族や地域の支えも力にして、元気に動き続けましょう
健康寿命を延ばし、笑顔のある未来を Wellbeベネッセレが取り組む介護予防・日常生活支援総合事業とは?
こんにちは! 山梨県で地域の健康づくりを支援するWellbeベネッセレです。 私たちは、「もっと自由に、もっと遊びを」という理念のもと、介護予防を通して地域の皆様が自分らしくいきいきと暮らせる毎日を応援しています。
今回は、当社が力を入れている「介護予防・日常生活支援総合事業」についてご紹介します。
介護予防・日常生活支援総合事業とは?
Wellbeベネッセレの介護予防事業は、単なる介護サービスにとどまりません。 利用者ご本人・ご家族・地域社会全体が健康で前向きな生活を送るための、包括的なサービスを提供しています。
「主なサービス内容」
1. 「遊々庵」ミニデイサービス
eスポーツやリラクゼーション、健康プログラムを通じて、楽しみながら身体と心を動かす場です。 地域の仲間とつながることで、孤立を防ぎ、生きがいを持った日常へつなげます。
2. 個別リハビリサービス
理学療法士が一人ひとりの状態を丁寧に評価し、パーソナライズされたリハビリを提供。 特に、フレイルや軽度認知障害(MCI)の予防に重点を置いています。
3. 自費サロン(自由参加型の健康づくり空間)
Nintendo Switchを使った運動やストレッチポールによるリラクゼーションなど、楽しく体を動かす“遊びの空間”を提供しています。
4. リエイブルメント(Reablement)に基づいた支援
「できることを取り戻す」ことを目的に、自立支援に特化した介入を行っています。 “介護される”ではなく、“やってみたい”を引き出すアプローチです。
Wellbeベネッセレが目指す未来
私たちが掲げる目標は、「健康寿命を延ばし、世代間の負担を軽減すること」です。 高齢化が進む今、フレイルやMCIといった介護予備軍の段階での介入が、将来の介護負担を大きく減らす鍵となります。
その中で特に重視しているのが、社会とのつながり。 誰かとつながり、楽しい時間を共有することが、身体的・認知的・心理的な健康の維持につながると私たちは考えています。
2025年OPEN! 「遊々庵 - ウェルネスサロン」
新たにスタートする「遊々庵 - ウェルネスサロン」では、テクノロジーと遊び心を活かした新しい介護予防を展開します。
特徴:
シニアに特化したやさしいゲームや運動プログラム
地域の人と自然に集えるカフェスペース
役立つ情報と交流が得られるワークショップや健康イベント
自分らしく、いきいきと生きるために Wellbeベネッセレの総合支援事業は、ただ「健康になる」ことを目指しているのではありません。 “楽しい” “また来たい”が続くことこそが、未来の介護予防につながると考えています。 「もっと自由に、もっと遊びを」 そんなあなたらしい健康のかたちを、私たちと一緒に見つけてみませんか?
お問い合わせはこちら
📞 電話番号:070-8549-2902
📩 メール:info@wellbebenessere.com
📢 無料体験・見学受付中

![ブログ更新:転倒リスク急上昇!雨の日の“安全な歩き方”と室内運動【山梨/デイサービス】]()