2025/10/31
親の転倒や認知症が心配なあなたへ【山梨/デイサービス】
「転ばないための正しい歩き方と運動講座」と「認知症にならない生活習慣講座」を行います!
最近、こんなことを感じていませんか?
✅親がよくつまずくようになった
✅歩き方が以前と違って見える
✅自分もなんとなく足が上がりにくい…
✅最近、物忘れが気になる
✅同じことを何度も聞いている
転倒や認知症は、要介護になる最大のきっかけと言われています。 でもその多くは、「歩き方」や「体の使い方」「生活習慣」を知ることで予防できます。
この講座では、理学療法士が以下の内容をやさしく、わかりやすくお伝えします。
📌 講座内容(60分)
✅転倒しやすくなる歩き方の特徴とは?
✅正しい歩き方と姿勢のポイント
✅自宅でできる簡単な予防運動
✅実際に歩いてみての歩行チェック体験
✅認知症になりやすい人の特徴は?
✅認知症を予防するための生活習慣は?
📌対象の方
✅ご両親の健康が気になる50〜60代の方
✅自分の将来のために、今できることを始めたい方
✅転ばない体づくりに関心のあるすべての方
✅認知症になりたくない人
🗓 講座開催情報
【日程】10月〜12月毎週水・木曜日 10:30〜11:30
【場所】遊々庵(山梨市正徳寺1513−2)
【定員】各回3名(予約制:先着順)
【参加費】無料
【申込方法】LINEまたはお電話で受付中
今のうちに「転ばないため、認知症にならないための一歩」を知っておきませんか?
ご家族のために、自分のために。お気軽にご参加ください。
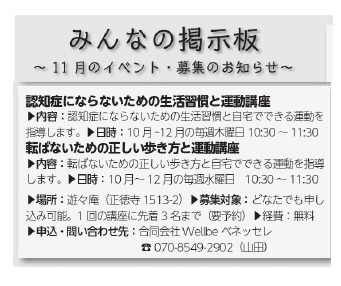
![親の転倒や認知症が心配なあなたへ【山梨/デイサービス】]()
2025/09/27
親の転倒が心配なあなたへ【山梨/デイサービス】
転ばないための正しい歩き方と運動講座を行います!
最近、こんなことを感じていませんか?
✅親がよくつまずくようになった
✅歩き方が以前と違って見える
✅自分もなんとなく足が上がりにくい…
転倒は、要介護になる最大のきっかけと言われています。 でもその多くは、「歩き方」や「体の使い方」を知ることで予防できます。
この講座では、理学療法士が以下の内容をやさしく、わかりやすくお伝えします。
📌 講座内容(60分)
✅転倒しやすくなる歩き方の特徴とは?
✅正しい歩き方と姿勢のポイント
✅自宅でできる簡単な予防運動
✅実際に歩いてみての歩行チェック体験
📌対象の方
✅ご両親の健康が気になる50〜60代の方
✅自分の将来のために、今できることを始めたい方
✅転ばない体づくりに関心のあるすべての方
🗓 講座開催情報
【日程】10月〜12月毎週水曜日 10:30〜11:30
【場所】遊々庵(山梨市正徳寺1513−2)
【定員】各回3名(予約制:先着順)
【参加費】無料
【申込方法】LINEまたはお電話で受付中
歩くことは毎日のこと。だからこそ、 今のうちに「転ばないための一歩」を知っておきませんか?
ご家族のために、自分のために。お気軽にご参加ください。
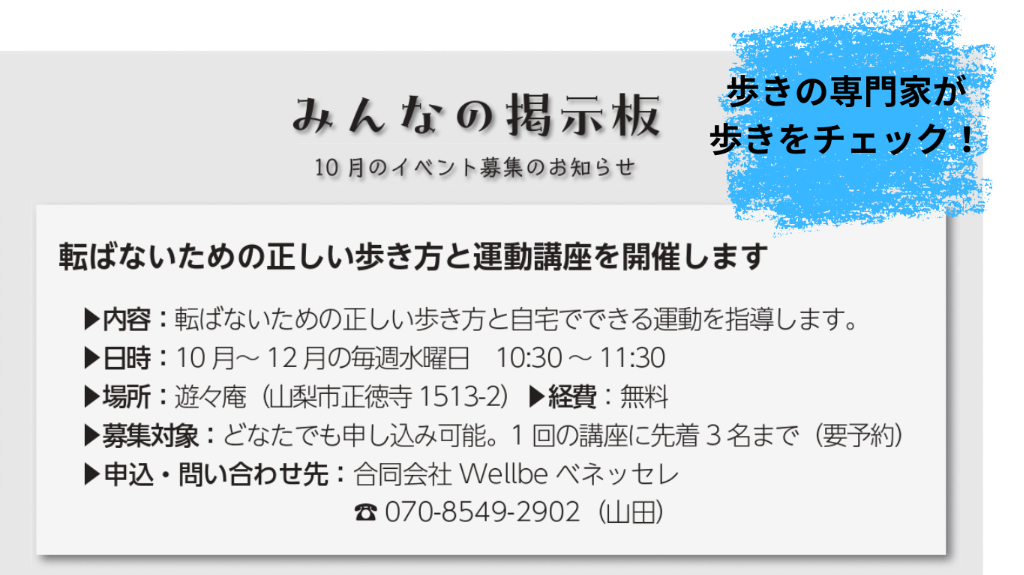
![親の転倒が心配なあなたへ【山梨/デイサービス】]()
2025/07/31
ブログ更新:猛暑に負けない体づくりを、家族と一緒に始めよう【山梨/デイサービス】
〜この夏、「介護予防」が身近なテーマになる〜
はじめに:「夏」は健康寿命を左右する季節 「暑いから外に出たくない」
「食欲がないから冷たい麺だけでいい」
「家族と話すのはお盆のときだけ」
──そんな日常が続くと、シニア世代の体と心は、想像以上にダメージを受けています。
実際に、猛暑の7月〜8月は「フレイル(虚弱)」が進行しやすく、介護が始まるきっかけとなる時期でもあるのです。
7月のブログでは、以下の6つのテーマを通じて「夏の介護予防」について掘り下げてきました。
・夏バテ防止と体づくり
・室内での筋力維持
・脱水と認知機能の関係
・夏の転倒リスク
・家族と行う介護予防運動
・冷房によるフレイルリスク
ここでは、それぞれのポイントを振り返りながら、8月以降に向けた「行動のヒント」をお届けします。
① 夏バテは“ただの疲れ”ではない
夏のだるさや食欲不振は、「年齢のせい」「この時期は仕方ない」と見過ごされがちです。
しかし、体の水分や栄養が不足した状態が続くと、筋力の低下や意欲の減退を招き、フレイルを加速させます。
特に重要なのが「タンパク質と水分の確保」。
冷たい麺類だけで済ませる食事では、筋肉を支える栄養が足りません。
▶ 対策例:冷奴・納豆・卵・魚・スープなどを意識して取り入れる
② 暑い夏でも、筋肉は待ってくれない
「運動は秋になってから」という考えは危険です。
シニア世代の筋肉は、わずか2週間の運動不足でも大きく減少すると言われています。
7月のブログでは、自宅でできるイス立ち上がり運動、片足立ち、足踏みなどを紹介しました。
▶ ポイント:冷房の効いた室内で、1日5〜10分からスタート
③ 脱水が脳にも悪影響を及ぼす
夏の水分不足は、脳への血流を減らし、注意力や記憶力を低下させることがあります。
「最近ぼーっとしている」「話がかみ合わない」などの症状がある場合、それはMCI(軽度認知障害)ではなく、脱水のサインかもしれません。
▶ 対策:1日1.5〜2Lの水分摂取を目標に。のどが渇く前に飲む習慣を。
④ 夏は転倒のリスクも高い
意外なことに、夏は「冷房による筋肉のこわばり」や「サンダル・スリッパでの歩行」「脱水によるふらつき」によって転倒リスクが高まります。
転倒は骨折や寝たきりのきっかけになるだけでなく、フレイル・要介護の入口とも言えます。
▶ 対策:イス運動・安全な靴選び・夜間照明の設置など、家庭内の環境整備を。
⑤ 夏休みは、親子で「介護予防」を始めるチャンス
7月の中旬以降は、夏休みに入り家族と過ごす時間が増えるご家庭も多いはず。
この時期を利用して、親子で一緒に体操や脳トレを楽しむことが、フレイル・MCI予防に大きく貢献します。
例)じゃんけんスクワット、お手玉キャッチボール、タオル引っ張り合いっこ
▶ メリット:会話と笑顔が増え、心の健康にもつながる。
⑥ 冷房の効きすぎに要注意
「快適さ=健康」と思いがちですが、冷房の効きすぎは活動量を奪い、結果として筋力低下に直結します。
また、冷房に頼るあまり、一日中椅子や布団で横になっていると、関節がこわばり、体が動かしづらくなるという悪循環にも。
▶ 対策:エアコンは26〜28度、1時間に1回は立ち上がる、軽運動を習慣に。
8月につなげたい「行動のヒント」
7月の学びを活かして、次の一歩を踏み出すために、以下のような「できること」から始めてみましょう。
【行動→内容】
・水分タイムを決める→10時・15時・寝る前など定時給水を習慣に
・運動タイムを設ける→毎日同じ時間に5分間の体操を続ける
・健康チェック→体重・握力・歩行速度など、簡易フレイルチェックを実施
まとめ:「健康は、暑い季節にこそ差がつく」
7月は、体力・筋力・認知機能が見えないうちに低下しやすい月。
この1ヶ月、「何もしていなかった」か「少しでも気をつけていた」かで、8月・秋以降の健康状態に差が出ます。
このブログを読んでいる今が、「生活を見直すチャンス」です。来月も、自分や家族の健康を守るために、小さな一歩からはじめましょう。
お知らせ:8月のテーマは「暑さと生活不活発病」
遊々庵では、8月も以下のような情報をお届け予定です。
・夏の生活不活発病と予防策
・お盆明けの“心と体のリズム”の整え方
・暑い時期でもできる栄養と運動の工夫
・健康講座・体験会のご案内 など
来月も引き続き、「健康寿命をのばす情報」をわかりやすく発信していきます!

![ブログ更新:猛暑に負けない体づくりを、家族と一緒に始めよう【山梨/デイサービス】]()
2025/07/27
ブログ更新:冷房の効きすぎが招くフレイルの危険〜快適さが健康を奪うことも〜【山梨/デイサービス】
はじめに:冷房が体を弱らせる?
暑い夏、エアコンは欠かせない存在です。
特に高齢者にとって、熱中症予防のための冷房使用は必須と言っても過言ではありません。
しかしその一方で、「冷房の効きすぎ」がもたらす健康への影響が、近年注目されています。
実は、涼しい部屋に長時間いることが、フレイル(虚弱)を進行させる原因になることもあるのです。
この記事では、冷房によるフレイルリスクと、健康寿命を守るための対策を詳しく解説します。
フレイルとは何か?〜冷房との関係を知る前に〜
フレイル(frailty)とは、年齢とともに筋力や体力、認知機能などが衰え、「健康」と「要介護」の間にある状態を指します。
放っておくと、転倒や寝たきり、認知症へと進行しやすくなるため、早期予防が重要です。
フレイルの主な原因は以下の3つ。
_筋力・運動機能の低下
_栄養不足
_社会的孤立・活動量の低下
冷房の効いた室内で長時間過ごす生活は、これらの要素と深く関係しています。
なぜ冷房がフレイルを招くのか?
① 筋肉や関節のこわばり
冷えた室内で長時間動かずにいると、筋肉が硬直しやすく、関節も動きにくくなる傾向があります。
その結果、動くのが億劫になり、活動量がさらに低下します。
② 運動量の低下 → 筋力の低下
快適すぎる空間は、身体を動かすきっかけを奪ってしまいます。
「暑い外に出たくない」「ずっと涼しい部屋で横になっていたい」
その結果、太ももやお尻の筋肉(下肢筋)が衰え、立ち上がりにくくなるのです。
③ 基礎代謝の低下
冷房環境では体温調節の必要が少なくなり、エネルギーの消費量も低下。
基礎代謝が下がると、食欲低下や活動意欲の減退につながり、栄養不足からフレイルへ進行します。
④ 社会とのつながりが減る
外出の機会が減ると、近所の人との挨拶や買い物といった日常の“社会参加”が減少。
結果として「誰とも話していない日が増える」=社会的フレイルへとつながる危険もあります。
室内にこもりがちな夏こそ意識したい「動ける体」の維持
では、冷房を使いながらもフレイルを防ぐには、どのような工夫が必要でしょうか?
以下に対策を紹介します。
フレイルを防ぐための5つの冷房対策+運動習慣
① 冷房は「快適+適度な温度」に設定
冷房の設定温度は 26〜28度が目安
冷えすぎを防ぐため、1〜2時間に一度は空気の入れ替えを
直接体に冷気が当たらないよう、風向きの調整もポイント
② 「座りっぱなし」を防ぐ生活リズム
1時間に1回、立ち上がってストレッチや水分補給をするだけでも違います。
・足踏み運動(その場で30秒)
・手足のぶらぶら運動
・肩まわし・首回しストレッチ
👉「ちょこちょこ動く」ことが筋力と代謝の維持に効果的。
③ 室内でできるフレイル予防運動 【運動名→効果→回数】
_イス立ち上がり運動→下肢筋力・転倒予防→10回×2セット
_片足立ち(安全第一)→体幹・バランス感覚→各足30秒×2セット
_タオル引っ張り運動→上半身・握力維持→10回×2セット
※無理のない範囲で、テレビを見ながらでもOK!
④ 食欲が落ちない工夫で栄養補給
冷房で動かない生活が続くと、自然と食事量も減ります。
そこで…
・冷奴、納豆、卵など消化に良いタンパク質を積極的に
・味噌汁、スープなどで 水分と塩分も同時補給
・少量でも栄養が摂れる 補助食品・プロテインも活用可
フレイル予防には、「動く+食べる」がセットです。
⑤ 家族や地域と“つながる”習慣を
・家族と一緒に体操タイム
・電話やLINEで会話を増やす
・デイサービスやサロンを活用する
「人と話す」ことも、身体と脳の刺激になります。
まとめ:冷房を正しく使って、夏を“元気に”乗り切る
冷房は、高齢者の命を守る重要なツールですが、過度な快適さは“動かない体”を作ってしまうこともあります。
✅冷えすぎに注意しながら、こまめに体を動かす
✅室内でも筋力維持の工夫をする
✅家族や地域とつながり、笑顔のある生活を保つ
これらが、健康寿命を延ばし、介護を遠ざける第一歩です。
お知らせ:遊々庵では「涼しい中でできる運動」プログラム実施中!
✅エアコン環境で行える軽運動
✅室内でできるフレイルチェックと体力測定
✅栄養と運動の両面からの介護予防サポート
「外は暑いけど、何もしないのも不安…」
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
“動ける夏”を一緒に過ごしましょう!

![ブログ更新:冷房の効きすぎが招くフレイルの危険〜快適さが健康を奪うことも〜【山梨/デイサービス】]()
2025/07/26
ブログ更新:夏休みこそ親子で始める介護予防:一緒にできる運動5選【山梨/デイサービス】
はじめに:「家族の時間」が健康をつくるチャンス
夏休みは、子や孫が帰省して家族で過ごす時間が増える貴重な季節。
このタイミングを活かして、「家族みんなでできる介護予防」を始めてみませんか?
高齢者の健康維持には「運動・栄養・社会参加」が重要ですが、
その中でも “誰かと一緒に行う運動” は、継続もしやすく、気持ちの面でも良い影響があります。
今回は、親子三世代で楽しく取り組める「介護予防につながる運動」を5つご紹介します。
家族の絆も深まり、健康寿命も延びる。そんな夏の習慣を、ぜひ今日からスタートしましょう。
なぜ「家族と一緒の運動」が効果的なのか?
1. 継続しやすい
「ひとりで運動しよう」と思っても、つい後回しになってしまいがち。
一緒に行うことで、声かけ・習慣化・励まし合いができ、運動を継続しやすくなります。
2. 孤立感の予防につながる
高齢者のフレイルやMCI(軽度認知障害)予防には、社会とのつながりが欠かせません。
家族との交流は「こころの栄養」となり、精神面でも良い影響があります。
3. 子どもにも好影響
子や孫にとっても、「おじいちゃん・おばあちゃんが健康でいてくれる」ことは安心感に。
予防の大切さを伝える教育的効果も期待できます。
一緒にできる!介護予防に効く運動5選
どれも室内ででき、運動が苦手な方や小さな子どもとも一緒にできるものばかりです。
① 立ち座りチャレンジ(太もも強化+転倒予防)
やり方:
・椅子に座り、背筋を伸ばす
・手を胸の前で組む
・ゆっくり立ち上がり、また座る(10回×2セット)
ポイント:
手すりを使ってもOK
お孫さんと「何回できるか」競争するのも楽しい!
② じゃんけんスクワット(反射+下肢筋力UP)
やり方:
・じゃんけんをする
・勝った人はスクワット1回、負けた人は2回!
・10回勝負で合計回数をカウント
ポイント:
ゲーム感覚で盛り上がれる
膝に負担のない範囲で行いましょう
③ お手玉キャッチボール(肩・腕の運動+脳トレ)
やり方:
・お手玉や丸めた新聞紙を交互に投げ合う
・キャッチしたら「好きな果物の名前」などテーマを決めて答える
ポイント:
認知機能+反応力+肩の運動が同時にできる
テーマを工夫して脳トレ要素を加える
④ タオル引っ張り合いっこ(体幹+握力トレーニング)
やり方:
・タオルの両端を親子で握り合い、引っ張る
・ゆっくり左右に引いたり、上下に動かしたりする
ポイント:
無理せず「引っ張り合いながら笑い合う」ことが大切
握力・体幹の維持に効果あり
⑤ テレビ体操・Switch体操ゲームを一緒にやる(継続しやすい運動習慣)
やり方:
・NHKのテレビ体操やYouTube動画を見ながら一緒に行う
・Nintendo Switchの「リングフィット」や「脳トレ」なども活用可
ポイント:
一人では続かなくても、家族で行えば続けやすい
運動が苦手な人でも、音楽やゲームの力で楽しめる
家族で取り組むことで得られる効果とは?
【効果→内容】
✅身体的効果→筋力維持・転倒予防・フレイル予防
✅認知的効果→注意力・記憶力の維持(MCI予防)
✅心理的効果→安心感・笑顔・ストレス軽減
✅社会的効果→会話が増え、孤独を感じにくくなる
親が元気になること=子の安心に。
子が支えてくれること=親の励みに。
こんな声が増えています(実際の利用者の例)
「娘と一緒にスクワットしたら、筋肉痛になりましたが、久しぶりに笑いました」
「孫とテレビ体操をしたのがきっかけで、今も毎朝続いています」
「家族が一緒にやってくれると、私も頑張ろうと思える」
こうした“きっかけ”は、小さな運動でも十分に価値があります。
まとめ:夏こそ、家族で「健康寿命」を育てる時間に
介護予防は、「いつか必要になるかもしれない」ではなく、「今のうちから備えるもの」です。
夏休みという特別な時間を使って、ぜひ親子で・三世代で、健康への第一歩を踏み出してみてください。
お知らせ:Wellbeベネッセレでも「家族でできる運動」教えています
私たちのサロンでは、
✅ 自宅でできる親子体操の紹介
✅ フレイルチェックと運動プログラム
✅ 介護予防講座や体験会 なども開催しています。
「この夏、家族で何かやってみたい」
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。

![ブログ更新:夏休みこそ親子で始める介護予防:一緒にできる運動5選【山梨/デイサービス】]()
2025/07/12
ブログ更新:夏の脱水症と認知機能低下の関係とは?〜シニア世代が気をつけたい水分管理〜【山梨/デイサービス】
はじめに:脱水は「命」にも「脳」にも関わる問題
暑い季節になると注意喚起される「脱水症」。
高齢者は若年層に比べて脱水になりやすいだけでなく、脱水が認知機能に悪影響を及ぼすこともわかってきています。
実際、脱水が進むことで「集中力の低下」「物忘れ」「ふらつき」など、MCI(軽度認知障害)や認知症と似たような症状が現れることがあります。
つまり、脱水は熱中症だけでなく、介護予防・認知症予防にも深く関わる重要なテーマなのです。
なぜ高齢者は脱水になりやすいのか?
理由① のどの渇きを感じにくい
加齢によって「口渇中枢」の感度が低下し、実際に水分が不足していても、のどの渇きを感じにくくなる傾向があります。
気づいた時にはすでに脱水が進行していることも。
理由② 体内の水分量が少ない
年齢とともに体内の筋肉量が減ると、体内に保持できる水分も少なくなります。
若い人に比べて、体が水分不足に弱くなっているのです。
理由③ 利尿薬や血圧の薬の影響
高齢者は高血圧や心疾患の治療で利尿作用のある薬を服用している場合も多く、気づかぬうちに体から水分が排出されています。
脱水が引き起こす「認知機能の一時的な低下」とは?
1. 軽度の脱水で「頭がぼーっとする」
脱水により脳への血流が低下すると、集中力・注意力が落ちるだけでなく、
「今何しようとしたっけ?」「あれ、何て言った?」という物忘れ症状が出ることがあります。
2. 中等度の脱水で「ふらつき・意識混濁」
中度以上になると、ふらつき・転倒・混乱など、MCIや認知症と区別がつかない症状に。
これを「脱水性せん妄」といい、特に高齢者では一時的に認知機能が大きく低下します。
3. 慢性的な軽度脱水が「脳の萎縮」につながる?
近年の研究では、慢性的な水分不足が海馬の委縮や認知症リスクに関係していることも報告されています。
脳の約75%は水分。脱水は脳の健康にも大きく影響しているのです。
認知症予防のための「正しい水分補給」のコツ
① のどが渇く前に飲む!
定時給水を意識
・起床後、朝食後、10時、昼食後、15時、夕食後、就寝前など
・毎日7〜8回の「水分タイム」をつくる
目安は1日 1.5〜2リットル(※腎疾患などある方は医師に相談)
② 飲みやすい飲み方を工夫
・お茶や水が苦手な方には 薄めたスポーツドリンクや経口補水液
・冷たい飲み物が苦手な方は 常温の麦茶や白湯 もおすすめ
・ゼリー飲料・スープ・果物 も水分源にカウントできる
③ 食事からも水分補給
【食品 → 水分含有率】
スイカ・メロン → 約90%
トマト・キュウリ → 約94%
豆腐・冷やし茶碗蒸し → 約80%
みそ汁・スープ → 約80〜90%
「飲む」だけでなく「食べて補う」視点も大切です。
ご家族が気をつけたい!脱水チェックのサイン
高齢のご家族が以下のような様子を見せたら、脱水を疑ってください。
✅ ぼーっとしている、返事が遅い
✅ 手の甲をつまんでもすぐに戻らない(皮膚のハリ低下)
✅ 尿の回数が少ない、色が濃い
✅ 倦怠感、めまい、ふらつきがある
✅ 会話がちぐはぐになったり、混乱した様子
このような症状は「認知症かな?」と思うかもしれませんが、実は脱水による一時的な影響の可能性もあります。
早めに水分を補給させ、改善するかを確認しましょう。
認知症・MCI・フレイル予防につながる「夏の習慣」
【習慣 → 目的】
・朝の水分+軽いストレッチ → 血流改善・意識覚醒
・10時・15時の給水タイム → 定時の水分補給で脱水予防
・昼食に味噌汁・果物を追加 → 食事からの水分+栄養補給
・毎日5分の室内運動 → フレイル・筋力低下予防
・夜の冷房と加湿管理 → 睡眠の質向上・夜間脱水防止
こうした 小さな積み重ねが、健康寿命を延ばし、将来の介護リスクを下げるカギになります。
まとめ:脱水と脳の健康はつながっている
「暑いから外に出ない」
「水分はあまり摂らない」
そんな生活が続くと、気づかないうちに脱水症→認知機能低下→転倒・入院と、連鎖的に悪化する恐れがあります。
今こそ、「水を飲むことは介護予防」という意識を持つことが重要です。
お知らせ:地域の取り組みも活用を 当サロンでは、夏の健康対策として
✅ フレイル予防講座
✅ 給水タイミングサポート
✅ 脱水チェック付きの個別運動プログラム
などもご用意しています。
「何をしたらいいか分からない…」という方こそ、気軽にご相談ください。 今の習慣が、5年後の自分を守ります。
次回は「シニア世代の転倒リスクが高まる夏の落とし穴」を予定しています。

![ブログ更新:夏の脱水症と認知機能低下の関係とは?〜シニア世代が気をつけたい水分管理〜【山梨/デイサービス】]()
2025/07/06
ブログ更新:フレイル予防は夏が勝負!暑さに負けない筋力維持法【山梨/デイサービス】
はじめに:夏こそ筋力が落ちやすい季節
「暑いから今日は運動お休み」
「外は危ないから、涼しい部屋で一日ゆっくりしよう」
そんな日が続く7月。気づけば体力が落ち、足腰が弱くなっている…
それが “フレイル” の始まりです。
フレイル(虚弱)は、健康と要介護の中間状態。
放っておくと転倒や入院をきっかけに一気に「要介護」へと進行する恐れがあります。
特に夏場は、暑さによる 活動量の低下 と 栄養不足 で、
筋肉量が急速に落ちやすい要注意の時期です。
今回は「夏にこそ意識したい筋力維持法」を具体的に解説し、
介護予防と健康寿命の延伸につなげるヒントをお届けします。
なぜ夏に筋力が落ちる?高齢者にとっての3つの落とし穴
① 外出機会の減少 → 歩かない・動かない
夏の炎天下を避けるあまり、買い物や散歩を控えがち。
涼しい室内で一日中過ごすことで、下半身の筋力低下が進みます。
特に太もも・お尻の筋肉が落ちると、「立ち上がれない」「転びやすい」といった状態に。
② 食欲低下 → タンパク質不足
暑さで食欲が落ちると、冷たい麺や果物だけの食事に偏りがちです。
すると、筋肉を維持するのに欠かせない タンパク質 が不足。
気づかないうちに筋肉量がどんどん落ちてしまいます。
③ 睡眠の質の低下 → 回復力の低下
熱帯夜が続くと、眠りが浅くなり疲労が蓄積。
体の回復機能が落ち、筋肉も修復されにくくなります。
結果として、全身のだるさや意欲低下がフレイルを進行させます。
今すぐできる!夏でも無理なく続けられる筋力維持の方法
① 室内でできる簡単トレーニング
冷房の効いた室内でもできる軽運動を紹介します。
毎日5分でもOK。継続がカギです。
▶ イスからの立ち上がり運動(10回×2セット)
_両手を胸の前で組む(手すりを使ってもOK)
_背筋を伸ばしてイスから立ち上がり、ゆっくり座る
_太もも・お尻の筋肉を意識
→ 下肢筋力アップ+転倒予防に効果的
▶ 片足立ち(左右30秒ずつ×2回)
_テーブルに手を添えながら安全に行う
_転倒防止のため、必ず支えのある場所で
→ バランス能力と体幹を鍛えられる
▶ 足踏み体操(1分間×3セット)
_テレビを見ながらその場で足踏み
_太ももを高く上げてリズミカルに
→ 有酸素運動+足腰強化に最適
② 食事の工夫で筋力の「材料」を補う
◎積極的に摂りたい栄養素
【栄養素→働き→含まれる食品】
_タンパク質→筋肉の材料→鶏肉、卵、豆腐、魚、納豆
_ビタミンB群→疲労回復→豚肉、玄米、レバー、枝豆
_ビタミンD→骨・筋肉の強化→鮭、しらす、干し椎茸
◎食が進まないときの工夫
_冷奴にしらす・オクラ・ポン酢:たんぱく質+ミネラル補給
_雑炊に卵+ささみ+刻みネギ:消化も良く、栄養バランス◎
_ヨーグルトにきな粉やはちみつ:おやつでもタンパク質がとれる
フレイルを防ぐための「1日モデルスケジュール」
時間帯→活動例
7:00 →起床・コップ1杯の水・軽いストレッチ
8:00 →朝食(卵・納豆・野菜入りみそ汁など)
10:00→室内で足踏み体操+片足立ち
12:00→昼食(魚の煮付け+ごはん+野菜)
14:00→昼寝(30分以内)・読書・趣味の時間
16:00→イス立ち運動・軽い筋トレ
18:00→夕食(豆腐ハンバーグ・野菜たっぷり)
21:00→入浴・ゆったりストレッチ・就寝準備
→このような 「規則正しい生活×筋力維持」 が、夏のフレイル予防に直結します。
地域での取り組みや家族のサポートもカギ
一人では継続が難しい場合は、以下のような外部サービスを活用するのもおすすめです。
_地域包括支援センター主催の体操教室やフレイル予防イベント
_通所型介護予防事業(総合事業A型など)
_パーソナルジムや健康サロンでの個別プログラム
_家族や孫と一緒に行う「共通運動タイム」など
💡 「誰かと一緒に行う」ことで習慣化しやすくなります。
まとめ:夏の習慣が、未来の自分を変える
暑さで動くのが億劫になる季節こそ、
「フレイル予防=健康寿命の守り方」 を意識することが重要です。
✔ 外出せずとも、室内でできる筋トレを毎日少しずつ
✔ 食事のバランスを整えてタンパク質をしっかり補う
✔ 家族や地域とつながり、楽しく続けられる仕組みをつくる
夏の過ごし方が、1年後・5年後の自分の体を決めるかもしれません。
「今年の夏こそ、フレイル予防の第一歩を踏み出しましょう!」

![ブログ更新:フレイル予防は夏が勝負!暑さに負けない筋力維持法【山梨/デイサービス】]()