2025/07/05
ブログ更新:猛暑に負けない体づくり:シニアのための夏バテ防止術【山梨/デイサービス】
はじめに:なぜシニア世代にとって夏は危険なのか?
7月、猛暑が続く季節。シニア世代にとって、この時期は熱中症や夏バテ、さらにはフレイル(虚弱)リスクが高まる危険な時期です。
特に高齢になると、体内の水分量が減少しやすく、のどの渇きを感じにくくなるため脱水に気づかないことが多いのです。
また、暑さで食欲が落ち、栄養不足や筋力低下が進むと、介護が必要になるリスクも高まります。
この記事では 「介護予防」「健康寿命の延伸」 をキーワードに、夏の健康管理法を詳しく解説します。
夏バテとは?高齢者に特有の危険性
夏バテは、暑さによる体温調節機能の乱れ、栄養・水分不足、睡眠不足が引き起こす体調不良です。
主な症状としては以下のようなものがあります。
_食欲不振
_倦怠感、だるさ
_頭痛、めまい
_下痢や便秘
_筋力低下、ふらつき
シニア世代では、これらの症状が進むと フレイルやMCI(軽度認知障害) のリスクも高まり、転倒・入院・介護生活のきっかけになりやすいのです。
夏バテ・熱中症を防ぐ!シニアの体づくり3つのポイント
① 水分補給を「意識的に」行う
シニア世代はのどの渇きを感じにくくなるため、
「のどが渇いたと感じる前に飲む」ことが重要です。
✅ 1日の目安は 1.5〜2リットル の水分補給(食事の水分含む)
✅ お茶やコーヒーだけでなく、経口補水液やスポーツドリンクを適度に活用
✅ 起床時・入浴前後・外出前後・寝る前に必ずコップ1杯の水を
② 栄養バランスを整え、筋力低下を防ぐ
夏バテで食欲が落ちると、タンパク質不足になり筋肉が落ちやすくなります。
以下の食材を積極的に取り入れましょう。
✅ タンパク質:鶏ささみ、豆腐、卵、魚
✅ ビタミン・ミネラル:トマト、キュウリ、オクラなど夏野菜
✅ 発酵食品:納豆、ヨーグルトで腸内環境も整える
💡 食が進まない時は、冷やしうどんにツナや卵をのせる、豆腐に薬味をたっぷりのせるなど、手軽に栄養が摂れる工夫を。
③ 室内での運動・体操で体力維持
暑さで外出を控えると、運動不足になり筋力低下・フレイルが進みます。
以下のような簡単な運動を毎日5〜10分取り入れましょう。
✅ 片足立ち(机に手をついてOK)
✅ イスからの立ち上がり運動
✅ 軽いスクワットや足踏み
✅ 両手を挙げて深呼吸
特に 太もも・お尻の筋肉を使う運動 は転倒予防・健康寿命の延伸に効果的です。
シニアのための「夏の生活習慣チェックリスト」
以下に当てはまる項目が多い方は、すぐに生活習慣を見直しましょう。
_のどの渇きを感じるまで水を飲んでいない
_日中ほとんど座りっぱなし
_食事はそうめんやパンなど炭水化物が中心
_冷房を強めにして一日中同じ部屋で過ごしている
_夜の寝苦しさで睡眠不足
1つでも当てはまれば、「夏バテ・フレイル予防」を意識した生活に切り替えるチャンスです。
まとめ:介護予防のために「今すぐできること」
夏は、シニア世代にとって健康寿命を左右する大切な季節です。
以下のことを意識して、猛暑に負けない体づくりを進めましょう。
✅ のどが渇く前に水分補給
✅ タンパク質・ビタミン豊富な食事を心がける
✅ 室内でも体を動かす習慣をつくる
健康的な毎日を送ることで、転倒や入院、介護生活のリスクを遠ざけることができます。
ぜひ 「家族みんなで支え合う夏の介護予防」 を意識してみてください。
最後に:地域での取り組みやサポートを活用しよう
当サロン(またはデイサービス・健康講座等)では、
猛暑を乗り切るための体操教室、栄養相談、フレイルチェックなども行っています。
気になる方はお気軽にお問い合わせください。
「まだ元気だから大丈夫」ではなく、「元気な今こそ予防」が大切です。

![ブログ更新:猛暑に負けない体づくり:シニアのための夏バテ防止術【山梨/デイサービス】]()
2025/07/01
🌿 7月のご挨拶と健康管理・介護予防のポイント【山梨/デイサービス】
皆さま、こんにちは。
平素より当施設の取り組みにご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
7月に入り、いよいよ本格的な夏の暑さが訪れる季節となりました。日差しが強く、蒸し暑い日が続くこの時期は、体調を崩しやすくなるだけでなく、活動量が減ることで体力や筋力の低下、認知機能の低下が進みやすくなる季節です。
私たちは、「暑さに負けず、心身ともに健やかに夏を乗り切る」をテーマに、7月も地域の皆さまの健康づくり、介護予防を応援してまいります。
今回は、7月ならではの健康管理のポイントと、介護予防のために意識していただきたい取り組みをご紹介いたします。ぜひ日々の生活にお役立てください。
☀️ 7月の健康管理で大切なこと
1️⃣ 熱中症・脱水症状を防ぐ
高齢になると、のどの渇きを感じにくくなり、気づかないうちに脱水が進むことがあります。特に室内にいても油断は禁物です。
✅ 1日1.2リットル以上の水分摂取を目安に、こまめに水分補給を心がけましょう。
✅ 水やお茶に加え、経口補水液やみそ汁、果物なども水分源になります。
✅ 室温は28度以下を目安にエアコンや扇風機を活用し、涼しい環境を保ちましょう。
2️⃣ 暑さで外出が減る→体力・筋力低下を防ぐ
暑さのために外出を控えると、知らない間に筋力・バランス力が落ち、転倒やフレイル(虚弱)のリスクが高まります。
✅ 室内でできる簡単な体操やストレッチを習慣にしましょう。
✅ 可能な方は、朝夕の涼しい時間帯に短時間の散歩を取り入れましょう。
✅ テレビを見ながら足踏み、立ち座り運動など「ながら運動」も効果的です。
3️⃣ 食欲低下への対策
暑さで食欲が落ちると、たんぱく質不足、栄養不足につながり、筋肉量が減りやすくなります。
✅ 冷たい麺類ばかりにならないよう、冷奴、納豆、卵、魚、肉などを少しでも加えましょう。
✅ 一度に食べられない場合は、1日3回以上に分けて少量ずつ食べるのもおすすめです。
🏃♂️ 7月の介護予防のためのおすすめ習慣
🌸 【運動】短時間でも毎日の積み重ねを
高齢期の介護予防では、「毎日少しずつ体を動かすこと」が大切です。
✅ 1回5分程度の軽い体操を1日数回行う
✅ 片足立ち(つかまりながらでOK)でバランス力を鍛える
✅ いすからの立ち座りを繰り返す
当施設でも、涼しい環境で無理のない範囲の運動プログラムを実施しています。 見学や体験も随時受け付けていますので、ぜひご相談ください。
🌸 【社会参加】孤立防止の工夫
暑さで自宅にこもりがちになると、人と会う機会が減り、認知機能の低下や意欲の低下につながることがあります。
✅ 電話やビデオ通話で家族や友人と話す
✅ デイサービス、サロンなど地域の集いに参加する
✅ 趣味の活動を続ける
当施設では、社会参加の機会として、eスポーツ、脳トレプログラムも取り入れ、楽しみながら介護予防ができる場を提供しています。

![🌿 7月のご挨拶と健康管理・介護予防のポイント【山梨/デイサービス】]()
2025/06/15
ブログ更新:カビだけじゃない!梅雨時に潜む“生活習慣病リスク”と対策法【山梨/デイサービス】
■ はじめに:梅雨時の「だるさ」と「体重増加」は見過ごせない
梅雨になると、こんな変化を感じませんか?
_体が重い・だるい
_食事が偏りがち
_雨で外出が減った
_なんとなく気分が落ちる
このような「小さな不調」は、実は生活習慣病のリスクを高める“入り口”でもあります。
梅雨は“カビ”や“湿気”にばかり目がいきがちですが、心と体のバランスを崩しやすい時期でもあります。
特にシニア世代にとっては、糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病が、筋力低下やフレイル、認知症のリスクに直結することも。
本記事では、梅雨時に気をつけたい生活習慣病リスクと、その具体的な対策をご紹介します。
■ なぜ梅雨は「生活習慣病の温床」になりやすいのか?
① 外出・運動量の減少
雨続きで散歩や買い物が減ると、1日の歩数が半分以下になることも。
筋力が落ち、代謝が下がり、体脂肪や血糖値が上がりやすくなります。
② 食欲の変動と偏食
蒸し暑さで食欲が落ち、冷たい麺類やお菓子、飲料に偏りがち。
これにより栄養バランスが崩れ、血糖コントロールや脂質代謝に悪影響を及ぼします。
③ ストレスと睡眠不足
低気圧や湿気による不快感や倦怠感は、交感神経を刺激し、血圧を上昇させることも。
また、寝苦しさや気分の落ち込みから、睡眠の質が悪化しやすくなります。
④ 水分摂取の減少
汗をかかない日でも体は水分を失っています。
脱水が進めば、血液がドロドロになり、高血圧や脳卒中のリスクも高まります。
■ 梅雨の生活習慣病リスクを放置すると…
梅雨時の「なんとなく不調」が続くと、以下のような悪循環に陥ります:
_動かない → 筋力低下 → 体重増加・糖尿病リスク↑
_食が偏る → 栄養不足 → 血圧や血糖が不安定に
_睡眠の質が下がる → 自律神経が乱れ → 高血圧や心疾患の原因に
さらに生活習慣病は、フレイルやMCI(軽度認知障害)のリスクを高めることも報告されています。
つまり、梅雨の体調管理は“未来の自立生活”を守るためのカギになるのです。
■ 今すぐできる!梅雨時の生活習慣病予防法 【3つの柱】
① 1日“室内1,000歩”を意識する
雨の日でも体を動かすことが何より大切。
テレビの前で足踏みしたり、室内を5分歩いたりするだけで血糖値や血圧の安定に効果があります。
▶おすすめ:
_朝・昼・夕それぞれ10分ずつ体を動かす
_階段昇降やスクワットも有効
_スマートフォンや万歩計で“動いた実感”を可視化する
② “1食1野菜”ルールで食事改善
食欲がない日こそ、野菜やきのこ、海藻などで“栄養の土台”を整えることが重要です。
▶具体策:
_サラダ or みそ汁に必ず野菜を入れる
_めん類だけで済ませない(+卵や納豆、わかめなどをプラス)
_甘いものより“噛みごたえのある”間食に切り替える(例:ナッツ、小魚)
③ 湿気に負けない“こころと体のリズム”をつくる
セロトニン不足やストレスによる睡眠の乱れを防ぐには、「光・音・動き」のリズムが鍵。
▶できること:
_朝起きたらカーテンを開けて、自然光を浴びる
_ラジオ体操や軽い体操で“朝の動きスイッチ”を入れる
_夜はスマホを早めに切って、1時間前から照明を落とす
■ こんな方は特に注意!
以下に当てはまる方は、梅雨時に生活習慣病が悪化しやすい傾向にあります:
_通院中(糖尿病・高血圧・脂質異常症など)
_1日1,000歩も歩かない生活
_食事が麺類中心
_朝昼の生活リズムが崩れている
_最近、体重や腹囲が増えている
■ ご家族や介護者の方へ:見守りのポイント
_ご高齢の家族が「今日は動かない」と言う日が増えていないか?
_食卓に“野菜”が並ばない日が続いていないか?
_水分を1日コップ5〜6杯以上とれているか?
_表情や会話が減っていないか?
こうした日常の変化が、生活習慣病やフレイル進行のサインになることがあります。
■ まとめ:6月の体調管理が「未来の健康寿命」を決める
梅雨はただの“ジメジメした季節”ではありません。
心も体もゆっくりとバランスを崩していく時期でもあります。
「なんとなくだるい」
「ちょっと食事が乱れてる」
「今日は動かなくてもいいか」
そんな“小さな妥協”を続けていると、生活習慣病が静かに進行していくかもしれません。
逆に言えば、今このタイミングで、食事・運動・生活リズムを少し整えるだけで、将来の病気や介護を防ぐことができるのです。
🌿おまけ:雨の日でも健康に過ごす“3つの工夫”
_小さな植物やアロマを置いて気分を上げる
_好きな音楽をかけて家事をしながら体を動かす
_食事に「彩り」と「噛む食材」を1つプラス

![ブログ更新:カビだけじゃない!梅雨時に潜む“生活習慣病リスク”と対策法【山梨/デイサービス】]()
2025/06/14
ブログ更新:体がだるい…それ、季節性うつかも?シニア世代の6月メンタル対策【山梨/デイサービス】
■ はじめに:6月の「なんとなく元気が出ない」に要注意
「朝起きるのがつらい」
「テレビを見る気になれない」
「誰とも話したくない」
そんな感覚を覚えたことはありませんか?
特にシニア世代の方にとって、梅雨時は気分が沈みがちになる季節です。
それは決して“気のせい”ではありません。
実際にこの時期は「季節性うつ(季節性感情障害)」が増えると言われており、
高齢者では「体がだるい」「やる気が出ない」などの“体調不良”として現れることも多いのです。
この記事では、6月の心と体の変化を読み解き、心の健康を保つための3つの習慣をご紹介します。
■ 梅雨どきに起こる“心の不調”の正体とは?
● 気圧と日照時間の変化が心に影響
梅雨は低気圧と雨が続き、自律神経が乱れやすい時期です。
また、日照時間が短くなることで、脳内のセロトニン(幸せホルモン)が減少し、気分が落ち込みやすくなります。
特に高齢者は、加齢によりホルモンバランスや神経調整力が低下しているため、
こうした変化に敏感に反応しやすい傾向にあります。
● 気分の落ち込みが「心だけ」で済まない理由
「心が沈む」状態が続くと、
→ 外出したくなくなる
→ 食欲が落ちる
→ 人と話さなくなる
→ 筋力も認知機能も低下していく
…といった “負のループ”に入りやすくなります。
これが続くと、フレイル(虚弱)やMCI(軽度認知障害)のリスクも高まります。
■ シニア世代の“心のセルフチェック”5項目
・朝起きたときに疲れがとれていない
・食欲があまりわかない
・外に出るのが億劫
・物事に興味がわかない
・最近、人と話す機会が減っている
※2つ以上当てはまる場合は、心のエネルギーが落ちているサインかもしれません。
■ 心を元気にする!シニアのための6月メンタル対策3選
① 朝いちばんの「光浴び習慣」
→ 起きたらまずカーテンを開けて自然光を浴びる。
たとえ曇り空でも、外の光は体内時計をリセットし、セロトニンを活性化させてくれます。
▶ポイント:
・朝7〜9時の間が効果的
・テレビをつける前に、まず“窓の外”を見る習慣を
② 「小さな外出」で心に風を通す
→ 5分の散歩でもOK。外の空気を吸い、違う景色を見ることで、脳と心のリフレッシュになります。
▶おすすめ:
・郵便ポストまで散歩
・近所の公園のベンチでひと休み
・雨の日はスーパーや公共施設の中を歩くのも◎
③ 「会話する」ことを習慣化する
→ 人とのやり取りが、脳と心の刺激になります。
一方的に話すテレビよりも、“双方向”のコミュニケーションが効果的。
▶アイデア:
・電話で家族や友人に連絡
・週1回の通いの場(サロンやデイサービス)を予定に入れる
・訪問ヘルパーや配達員さんと「ひと言多く話す」習慣も◎
■ フレイル・認知症・うつ…そのつながりとは?
「気分の落ち込み」は、筋力低下(フレイル)や認知機能の低下(MCI)と密接に関係しています。
・気分が落ち込む → 動かない → 筋力が落ちる
・人と話さない → 脳が刺激されない → 認知機能が落ちる
・食欲がわかない → 栄養不足 → 体も脳も弱る
つまり、心の健康を守ることが、体と脳の健康を守ることにつながるのです。
■ ご家族・介護者の方へ:こんなサインに気づいたら声かけを
・部屋が暗いまま、日中も電気をつけていない
・表情に元気がない
・同じ服を何日も着ている
・食事をほとんど取っていない
・会話が一言、二言で終わる
これらは、心の元気が失われているサインかもしれません。
無理に外出させるより、「一緒に散歩しない?」「コーヒー飲もうか?」と自然な声かけが効果的です。
■ まとめ:6月は“心のケア月間”に
梅雨の時期は、知らず知らずのうちに心が疲れやすくなる季節です。
でも、日々の暮らしにちょっとした“光と会話と動き”を取り入れるだけで、心の状態は大きく変わります。
6月は、「自分の心の声」に耳を傾けて、心の健康にも“予防”の目を向けるチャンスです。
☂️ おまけ:「気分が沈む日」におすすめの小さな楽しみ5選
・いつもよりちょっと高級な紅茶を淹れる
・昔のアルバムを眺める
・ラジオを流しながらストレッチ
・窓辺の観葉植物に話しかける
・YouTubeで昭和歌謡を一緒に歌う

![ブログ更新:体がだるい…それ、季節性うつかも?シニア世代の6月メンタル対策【山梨/デイサービス】]()
2025/06/08
ブログ更新:実は6月が危ない!?“認知機能の低下”と気象の関係【山梨/デイサービス】
はじめに:梅雨になると「物忘れ」が増える?
「最近なんだか忘れっぽい…」
「話の途中で言葉が出てこない…」
そんな小さな変化を感じたことはありませんか?
実はそれ、気象の変化と関係しているかもしれません。
6月は、1年の中でも「認知機能の低下」が起きやすい時期とされています。
特にシニア世代では、季節の変わり目や気圧の変化によって、気分や集中力が下がりやすく、脳の働きにも影響が出ることが知られています。
この記事では、6月に起こりやすい認知機能低下のメカニズムと、MCI(軽度認知障害)や認知症の予防のために今できることを、わかりやすくお伝えします。
気象が脳に与える影響とは?
● 低気圧が引き起こす 「脳のだるさ」
梅雨時は低気圧や高湿度の日が続きます。すると、自律神経が乱れやすくなり、「なんとなくだるい」「頭がぼーっとする」といった状態が起こります。これは、脳の血流が低下することで、神経伝達が鈍くなるためです。
特に高齢者は、加齢により血流や代謝が低下しているため、天気の影響を受けやすい傾向にあります。
● 日照時間の減少とセロトニン不足
6月は曇りや雨の日が多く、日光を浴びる時間が激減します。これにより、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌が減少。
セロトニンは、気分の安定や記憶力にも関係しており、不足すると不安感やうつ状態、注意力の低下を引き起こすとされています。
● 運動不足と脳への刺激減少
雨が続くと外出や運動の機会が減少します。すると、脳への刺激も同時に減ってしまうため、活性化が妨げられます。これは、認知機能に必要な“脳の可塑性”(使うことで成長する力)を低下させる要因になります。
MCI(軽度認知障害)とは?見逃されやすい初期サイン
MCIとは?
MCI(Mild Cognitive Impairment)とは、「認知症ではないが、年齢の割に記憶力や思考力が低下している状態」です。放っておくと、5年以内に約半数が認知症に進行すると言われています。
よくある初期サイン
_同じ話を何度もする
_人の名前や約束を思い出せない
_新しいことが覚えにくくなる
_慣れた場所で迷う
_複雑な作業が億劫になる
これらは、日常生活で「ちょっとした違和感」として表れます。梅雨の体調不良と重なると、「ただの疲れかな」と見過ごしてしまうことも多いのが現実です。
6月に意識したい!脳を守る3つの習慣
① 「朝の日光」を浴びる 天気が悪い日でも、朝起きたらカーテンを開けて外の光を浴びることが大切。
これにより体内時計が整い、セロトニンの分泌が促されます。
▶ポイント:
・起床後30分以内に窓際で3分〜5分程度光を浴びる
・曇りの日でも効果あり!
② 「会話」を意識的に増やす 人と話すことで、記憶を引き出したり、言葉を選んだりする脳の領域が活性化します。
梅雨時に引きこもりがちになると会話の機会が減るため、意識して会話を作る工夫を。
▶方法の例:
・電話で家族や友人と近況報告
・テレビの感想を日記に書く
・デイサービスやサロンを活用して雑談の場を増やす
③ 「脳トレ運動」で一石二鳥
脳に良いと言われる運動は、体と頭を同時に使う運動です。
たとえば、「足踏みしながら数字を数える」「スクワットしながらしりとりをする」など。
簡単な運動に“認知課題”をプラスするだけで、記憶力や判断力を刺激できます。
▶おすすめ:
・Nintendo Switchなどを活用した脳活系ゲーム(特にシニア向けソフト)
・デイサービスや地域サロンでの体操+ゲームの組み合わせ
認知症予防は“季節ごとのケア”がカギ
6月のように、気分が落ち込みやすく、活動量が減る時期は、「無意識のうちに認知機能に負担がかかる時期」です。
そのため、年中同じ生活ではなく、季節ごとのセルフケア戦略が重要になります。
・冬は防寒と生活不活発症対策
・春は花粉症や生活リズムの乱れ対策
・梅雨は心身の停滞による脳機能の鈍化に注意!
・夏は熱中症と脱水による意識低下防止
季節に合わせて認知症予防のスイッチを入れ替えることが、健康寿命を延ばす近道です。
まとめ:6月は“見えない脳疲労”に気づくタイミング
6月は「何となく調子が出ない」という方が多い時期です。
けれど、それを放っておくと、脳にも“だるさ”が蓄積し、思考力や記憶力の低下につながる可能性があります。
まずは、「朝の光」「人との会話」「軽い脳トレ運動」からスタートしてみましょう。
認知機能の低下は、早めに気づいてケアすることで、予防・改善が可能です。
天気に左右される6月だからこそ、自分自身の“脳のコンディション”に目を向けてみませんか?
🧠おまけ:雨の日におすすめ!5分でできる脳活体操
・両手で同時に違う形を描く(例:右で三角、左で丸)
・昨日の食事を思い出しながらスクワット
・「赤い果物」「四角い文房具」などカテゴリーしりとりを声に出す
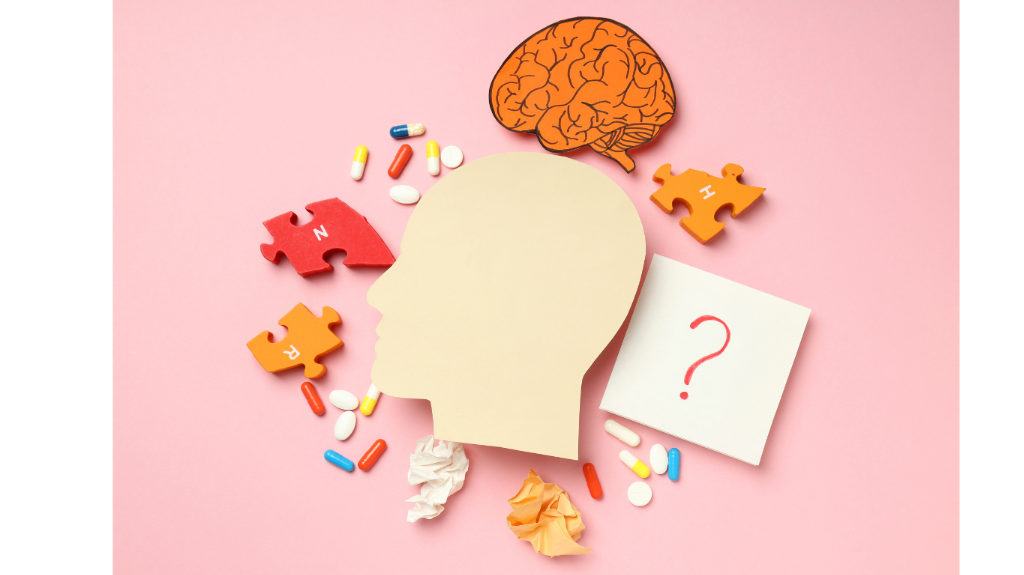
![ブログ更新:実は6月が危ない!?“認知機能の低下”と気象の関係【山梨/デイサービス】]()
2025/06/07
ブログ更新:梅雨時の“動かない生活”が危険!筋力低下を防ぐ家トレ3選【山梨/デイサービス】
はじめに:梅雨の生活、こんな変化に気づいていますか?
梅雨の季節になると、「なんとなくだるい」「外に出るのが面倒」「動く機会が減った」と感じる方が増えてきます。特にシニア世代では、気づかぬうちに体を動かす習慣が減り、それが筋力低下やフレイル(虚弱)につながることも。
実は6月は、季節の中でも“最も運動不足になりやすい時期”と言われています。
さらに、雨による気分の落ち込み、関節の痛み、湿気による体調不良なども加わり、「なんとなく動かない」が続くことで、筋力は徐々に落ちていきます。
そこで今回は、梅雨時こそ取り入れたい「家でできる簡単トレーニング3選」をご紹介。
外に出られない日でも、体を動かす習慣を守るための第一歩を踏み出しましょう!
なぜ梅雨時に筋力低下が起きやすいのか?
● 外出機会の減少
雨が続くと、散歩や買い物など、日常の活動量が一気に減ります。特に高齢者は転倒のリスクを考え、外出を避けがちです。これにより、脚の筋肉を使う機会が減少し、筋力低下が進行しやすくなります。
● 気分の落ち込み(気象病)
低気圧や湿気による「気象病」で、体のだるさや関節痛、やる気の低下が見られる方も少なくありません。すると、気持ちがふさぎがちになり、「今日は動かなくてもいいか」と活動意欲が低下します。
● フレイルの始まりに気づきにくい
「疲れやすい」「歩くスピードが遅くなった」など、最初のフレイルの兆候は、気候のせいと思われがち。結果として、「年齢のせいだから仕方ない」と予防行動をとらずに放置してしまうリスクがあります。
自宅でできる!梅雨時の筋力低下を防ぐ家トレ3選
① スクワット(椅子を使った安全バージョン)
効果:下半身(太もも・お尻・体幹)
椅子の前に立ち、手すりやテーブルでバランスを取りながら、ゆっくり座る→立ち上がるを繰り返します。 膝に負担がかかりすぎないように、深くしゃがまないのがポイント。
▶目安:1日10回×2セット
▶ポイント:背中を丸めず、目線は前へ
② かかと上げ&つま先上げ運動
効果:ふくらはぎとすねの筋肉 → 転倒予防に◎
つま先を地面につけたまま、かかとを持ち上げて数秒キープ。次に、かかとをつけたまま、つま先を上げてキープ。これを繰り返すことで、ふくらはぎや足首の筋力がアップします。
▶目安:各10回ずつ、1日2〜3セット
▶ポイント:壁や椅子に手を添えてバランスをとる
③ 肩甲骨まわし&胸開き体操
効果:猫背予防、呼吸改善、全身の血流促進 手を肩にあて、肘で大きく円を描くように回します。その後、手を後ろに引いて胸を開く動作を数回。姿勢の改善と血流アップで、気分も前向きに。
▶目安:10回×2セット(前・後ろ)
▶ポイント:呼吸を止めず、ゆっくり丁寧に
日常にどう取り入れる?継続のコツ
朝のルーティンに組み込む
→ 朝の天気が悪い日は気分が下がりやすいので、簡単な体操で1日をスタート。
テレビを見ながら、○○しながら運動
→ “ながら運動”で無理なく継続。CM中のスクワット、ニュースを見ながらのつま先上げなど。
家族と一緒にやる時間をつくる
→ 夫婦で同時に行ったり、子どもや孫とビデオ通話をつなげて“見守りながら運動”するのも◎。
まとめ:動かない6月が、老化を進める6月になる前に
梅雨時は、つい「今日は休んでもいいか」と思ってしまう日が続く季節です。
でも、その「動かない1日」が1週間、1ヶ月と続けば、“気づかぬうちに体が動かなくなる”悪循環が始まります。
筋力は年齢とともに自然に落ちるものですが、「動かし続ける」ことで、維持・回復は可能です。
特に下半身の筋力低下はフレイルや要介護の入り口とも言われています。
6月の梅雨こそ、家の中でできる運動で、自分の健康寿命を守る一歩を踏み出しませんか?
☔おまけ:梅雨のやる気が出ないときの習慣3つ
・部屋のカーテンを開けて、光を取り入れる
・好きな音楽を流しながらストレッチ
・運動後はお気に入りのハーブティーやおやつで自分にご褒美
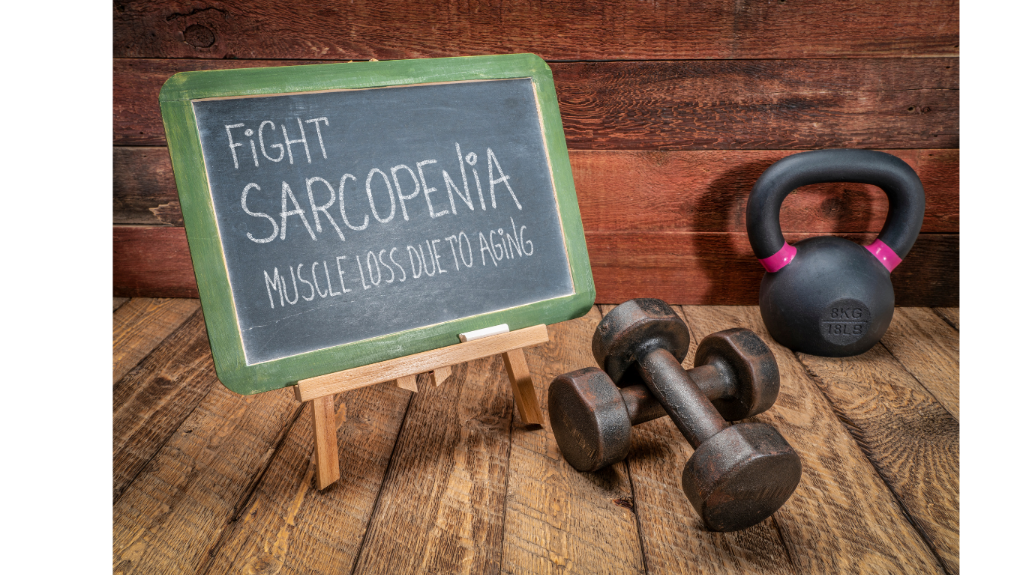
![ブログ更新:梅雨時の“動かない生活”が危険!筋力低下を防ぐ家トレ3選【山梨/デイサービス】]()
2025/06/01
ブログ更新:今日から6月!梅雨入り前に見直したい、心と体のコンディション【山梨/デイサービス】
はじめに
こんにちは!今日から6月が始まりました。
年の前半も折り返しに入り、気温も湿度も少しずつ上がりはじめるこの時期。気づかぬうちに、心や体に「だるさ」や「疲れ」がたまっていませんか?
6月は「梅雨入り」や「蒸し暑さ」が本格化し、外出が減り、活動量も落ちやすくなる季節です。
特に高齢者にとっては、筋力の低下やフレイルの進行、そして気分の落ち込みなど、注意すべきリスクが増える月でもあります。
今回は、“6月のはじまり”という節目に、ご自身の体と生活習慣を見直すきっかけとなるよう、これからの季節を元気に過ごすためのヒントをご紹介します。
1. 6月はどんなリスクがある?
✅ 雨が多くなり、外出が減る
→ 活動量の低下=筋力低下=転倒リスク増加
✅ 気温・湿度の上昇で疲れやすくなる
→ だるさ・食欲不振・睡眠の質低下
✅ 気圧の変化で気分が落ち込む
→ やる気が出ない、何となく不安になる
➡ これらが重なると、身体的にも精神的にも“下り坂”に入りやすいのが6月です。
2. 今日からできる6月の介護予防習慣
(1)「梅雨でも動ける」室内運動習慣
雨の日に備えて、室内でもできる運動を習慣にしましょう。
・椅子スクワット(太もも・お尻強化)
・もも上げ運動(バランス機能向上)
・足指グーパー(足裏から全身を活性化)
➡ 朝・昼・夕方など、時間を決めて取り組むと習慣化しやすくなります。
(2)食欲がない日でも「たんぱく質+水分」は死守
暑さで食が進まないときも、最低限以下は意識しましょう:
「食べ物→摂れる栄養」
・ゆで卵、納豆→良質なたんぱく質
・味噌汁、スープ→水分+塩分補給
・ヨーグルト→たんぱく質+消化サポート
・きゅうり、トマト→水分たっぷりで食べやすい
➡ 「ゼリーやプリンなど“食べる水分”も活用」して、水分&栄養の確保を意識しましょう。
(3)朝の“光”と“音”でリズムを整える
梅雨時は、日照時間が減り、生活リズムが乱れやすくなります。
・朝カーテンを開けて日光を浴びる ・好きな音楽を流して1日をスタート
・軽い体操で“やる気スイッチ”をオン
➡ 「リズムが整えば、気分も整う」特に認知機能や感情の安定に効果的です。
3. 家族・周囲と“ゆるくつながる”6月のすすめ
雨で外出が減ると、孤独感や社会的な孤立感が高まりやすいのも6月の特徴です。
・電話やLINEで定期的に声をかける
・地域の体操教室やサロンに誘ってみる
・買い物や通院に“付き添い”ではなく“一緒に楽しむ”視点で関わる
➡「関わりすぎない、でも切らさない」ゆるいつながりが心の支えになります。
4. 6月は「備える月」。夏に向けた準備を始めよう!
梅雨が明ければ、いよいよ本格的な夏が始まります。
夏バテ・熱中症・脱水といったリスクに備えて、6月は「予防の助走期間」ととらえましょう。
「今からできる備え→理由」
・室内での軽運動習慣→夏の筋力低下を予防
・水分補給と塩分管理→熱中症対策の基本
・睡眠と食事の見直し→自律神経の安定化に効果」
まとめ:6月のはじまりは、「生活の土台」を整えるチャンス!
✅ 気候の変化に流されず、「自分のリズム」を大切に
✅ 雨の日でも“動く・食べる・笑う”習慣を崩さない
✅ 7月・8月の暑さに負けない体と心を今から準備
6月は、静かに健康格差が広がり始める時期でもあります。
「動ける人」と「動かない人」、「つながれる人」と「孤立する人」では、3か月後の体調に大きな差が生まれるのです。だからこそ、今日という“6月のスタート”を、「備えるきっかけの日」にしてみませんか?

![ブログ更新:今日から6月!梅雨入り前に見直したい、心と体のコンディション【山梨/デイサービス】]()